
2025(令和7)年4月
熊谷守一の『へたも絵のうち』は、日本経済新聞のコラム〈私の履歴書〉に1971(昭和46)年6月から翌月まで連載された文がもとになっています。以下には、同書から岐阜時代のことをご紹介します。
◇
父のことと兄のこと
三百年ほど前に、先祖が「関の熊谷」をついでから、私の家系は三代目ごとに破産したといわれています。ただ破産するくらいだから、それなりの財産はあったのでしょう。ともかくいつのころからか、村では大きな地主だったようです。そして、だれかが破産しても、次かその次がまた、なくした土地や山林を取り返して大きくなっています。
(村の顔役然となった)父はそんなことで新しい世の中の見聞を広めたのか、村に帰ってからは、いろいろなことに手を出しました。私の生まれる前には、「春牛社」というしゃれた屋号で牛を飼い牛乳を売ったこともある。(中略)「春牛社」の前には、紺屋もやった。地主でありながら、じっと手をこまねいてはおれなかったらしいのです。何もしないでじっとしていることがいちばんだと考えている私とは、大違いの性分です。
私は七人兄弟の末っ子ですが、兄弟はむろんいまはみんないません。男は三人で、一番上の兄は、のち慶応大学を出て家を継ぎました。二番目の兄は、ちょっと変わりものでした。やはり慶応の中等部くらいは行ったようですが、あんまり性格がやさしすぎる、というより気の弱すぎる人でした。
「岐阜の家」
四つの年、私はこの付知の家から、「岐阜の家」に移されました。父の経営する製糸工場のすぐ隣にもう一つ父の家があって、そこにも大ぜいの人が住んでいたのです。その大ぜいの住人の内わけは、はっきり記憶にありません。ともかく、父の妾が二人いました。そしてその子供たち、つまり私の異母兄弟に当たる人が数人。さらに妾の姉妹だとか、はっきりしない係累が、ごちゃごちゃとたくさんいました。
岐阜に移されたばかりのころは、祖母が私に会いたいからといって、よく付知に連れ戻されました。しかしすぐ追いかけるように男衆が迎えに来て、私はウムをいわせず背中にくくりつけられて、歩いて二日の道を岐阜の家に戻されたのです。母はいたっておとなしい人で、すべて父のいいなりでした。
私はもう小さいときから、おとなのすることはいっさい信用できないと、心に決めてしまったフシがあります。子供といっても、何でも理解して確信をもって判断してしまうものです。(中略)ただ、威張っていない方の妾の妹だけは、よくなつきました。その人と一緒に、近くの小川に小魚をとりに行くのが、楽しくて仕方がない。くわしいことはおぼえていませんが、陰でよく私をかばってくれてもいたようです。
小学校に上がっても、先生の言うことなど、ほかの子供のようによく聞く気にはなれないのです。とくに、師範の付属だから先生は若い人が多く、まともに相手にはできない気持ちでした。(中略)先生は、しょっちゅう偉くなれ、偉くなれといっていました。しかし私はそのころから、人を押しのけて前に出るのが大きらいでした。
私は子供のころから、こわいものはほとんどありませんでした。人にこびたり、逆に人を押しのけて前に出ることはしなかったから、こわいと思う人などいないのです。先生にしかられても、こちらは別に悪いことはしていないと思っているので、こわいとは思いません。
徴兵検査は、(本郷森川町の共立美術)学館に通っている間に受けて、丙種でした。からだは丈夫だし体格も良かったのですが、歯がひどく悪く、それで丙種になったのです。今では、歯ぐらい悪くともなんともないでしょうが、そのころは歯がたくさん抜けていると(私は六、七本抜けていました)とやかくいわれたのです。しかし今からみれば、丙種になったのは幸いでした。というのも、四年後の明治三十七年に起きた日露戦争で、甲種では戦死した人が多いのです。岐阜の中学の同級生は、私ともう一人を残して、他はすべて旅順の攻防戦などで死んでいます。残ったもう一人も、重傷を負って、気がふれた感じになってしまいました。私も歯が抜けていなかったら、赤い夕日の満洲のどこかではてていたことでしょう。
◇
熊谷守一は、20歳で旧制・東京美術学校(現・東京芸術大学美術学部)の西洋画科選科に入りました。同校は、文部省から欧米に派遣された岡倉覚三(天心)、E.フェノロサの報告をもとにして1887(明治20)年に設立されました。1889(明治22)年の開校時には、初代校長は岡倉、副校長をフェノロサが務め、教官には橋本雅邦や高村光雲らが迎えられました。1893(明治26)年の第一期卒業生には横山大観らがいました。1896(明治29)年には西洋画科、図案科が新設され、岡倉退任後の1905(明治38)年には校制改革が行われました。熊谷は、そうした時代に学びました。
熊谷は豊島区千早に自邸を建て、1932(昭和7)年から家族と共に暮らし始めました。当時のこの辺りは野原と畑で、遙かに上野の方まで見通せたとのことです。家にはアトリエと庭もあり、庭は熊谷と妻が育てた植物で森のようになりました。
次の写真は、現在の豊島区立熊谷守一美術館で、熊谷が亡くなった1977(昭和52)年まで暮らした家の跡地に次女の榧が私設美術館を創立したものです。

以下、再び『へたも絵のうち』から引用します。
そのころの美術学校には、変わった人がたくさんいたものです。私の級ではないが、絵かきの学校にきているのに、絵筆を一本しか持たない男がいました。その一本で、なんとかこねくり回して絵をかいている。ところがこの男、帰る段になると方向が一定しない。足の向くままというかっこうで、一人でスタスタどこかに消えてしまいます。
戦後の話ですが、夕暮れの太陽だけをカンバスの真ん中に描いた絵を展覧会に出したら、武者(小路実篤)さんはそれが気に入らなくて、「そんなアホらしい絵をよく平気で出すな」と言っていました。黒のバックの真ん中に薄い桃色とオレンジ色で丸い太陽を描いたもので、私はおかしくはないと思うのですが、武者さんは断じておかしいといったそうです。私はこの絵を「自画像」と言っていました。私も人生の夕暮れに立っているので、そう言ったのです。これより前に、泥の塊を描いた「土塊」(つちくれ)という絵も、「自画像」と称したこともあります。
人間というものは、かわいそうなものです。絵なんてものは、やっているときはけっこうむずかしいが、でき上がったものは大概アホらしい。どんな価値があるのかと思います。しかし人は、その価値を信じようとする。あんなものを信じなければならぬとは、人間はかわいそうなものです。
最近は書もよく書きます。頼まれて何か好きな字を書けといわれたときは、「独楽」「人生無根蔕」「無一物」「五風十雨」などと書きます。根蔕の「蔕」は柿やナスビのヘタのこと、「五風十雨」は五日に一度風が吹いて十日に一度雨が降るという、それだけの意味です。(中略)なるべく書きたくないのは「日々是好日」とか「謹厳」などという字です。しかし妻がいうには、無理に頼まれて書いても、あとで展覧会などで見ると、本人が喜んで書いたように見えておかしいそうです。
よく行ったのは、房州の太海、伊豆一帯、信州の八ケ岳、渋温泉などです。山下新太郎らと大島に行ったこともありました。式根島もあります。しかし、一般にあんまり景色のいいところは私には向きません。広島の厳島でも絵を描く気にはなれませんでしたが、山形の蔵王でも、やっぱりダメでした。描いてはみたが、思うようには仕上がらない。むしろ、書生さんたちが「こんなところは二度と来るものか。とても絵にはならん」などと言って怒るような場所が私には合います。別にひねくれているわけではないが、しぜんとそうなるから不思議です。
ただ何回かふれましたが、私はほんとうに不心得ものです。気に入らぬことがいっぱいあっても、それにさからったり戦ったりはせずに、退き退きして生きてきたのです。ほんとうに消極的で、亡国民だと思ってもらえばまず間違いありません。
私はだから、誰が相手にしてくれなくとも、石ころ一つとでも十分暮らせます。石ころをじっとながめているだけで、何日も何月も暮らせます。監獄にはいって、いちばん楽々と生きていける人間は、広い世の中で、この私かもしれません。
人は私のことをよく、「仙人だ、仙人だ」というようですが、そういわれると、ああこの人は何かよくないことをたくらんでいるのかな、と思ってしまいます。自分はふつうの人だから、よくないことでも何でもするが、お前は仙人だから…といって、ズルイことをされたことは何回かあるようです。だから、仙人だといわれると、身構える感じになってしまう。
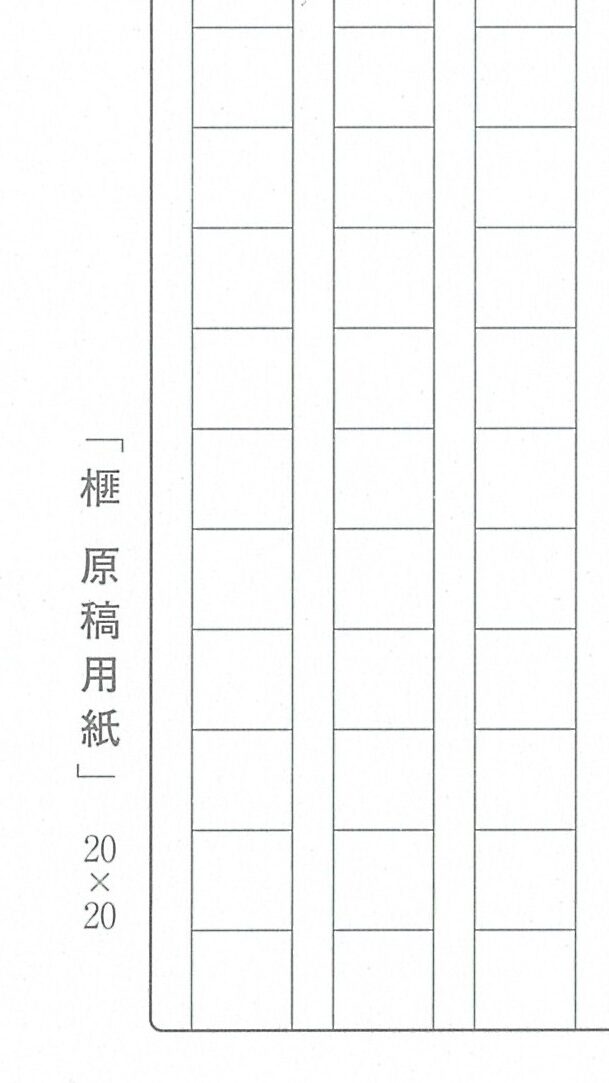
(熊谷榧が執筆に使ったのと同じ原稿用紙、豊島区立熊谷守一美術館にて)
参考文献
「平凡社ライブラリー325 へたも絵のうち」熊谷守一著(平凡社、2018年)
岐阜県立岐阜高等学校・同窓会事務局 岐阜市大縄場3-1 岐阜高校・校史資料室内

